このブログは、主に宇宙を題材にしたSF小説の中から、科学や物理に関連するトピックを選んでわかりやすく解説します。宇宙に興味のある方はもちろん、これまでSFを読んだことのない方にも、科学の扉を開くきっかけになる事を目指しています。読む時間は5分程度なので、ちょっとしたスキマ時間で気分転換になると思います。そして小説を読んだ後にもう一度この記事を読むと「なるほどー」な感覚が楽しめますよ。
今回は、SF作家ジェイムズ・P・ホーガンの『ガニメデの優しい巨人』から2500万年前の話です。
これは『星を継ぐもの』という小説の続きの話です。物語では、木星の衛星ガニメデで、とても古い宇宙船が見つかります。その中にはなんと、2500万年前の地球の生き物たちが積まれていたのです!
の哺乳類-683x1024.png)
2500万年前の地球ってどんな時代?
この時代は「漸新世(ざんしんせい)」と呼ばれています。
恐竜が絶滅したのは約6600万年前。そのあと、地球では哺乳類が大きくなり、いろいろな種類に進化しました。たとえば、ウマの祖先のメソヒップス、サイの祖先のパラケラテリウム、そして私たち人間の祖先につながる霊長類(れいちょうるい)などです。
ケニアの地層からは、この時代の類人猿(人間に近いサル)の化石も見つかっています。小説の中でも、この類人猿が宇宙船に乗せられてガニメデに運ばれた、というストーリーが描かれています。
日本列島ができはじめたころ
2500万年前の日本は、まだアジア大陸とくっついていました。でもそのころから、大地が少しずつ引き裂かれ始め、日本海ができはじめたのです。火山の活動も活発で、今の日本列島のもとになる大地が作られていきました。
人類の祖先が二足歩行を始めた理由
この時代には、サルから類人猿へと進化する分かれ道がありました。
そして1500万年前ごろ、アフリカの森が少なくなりはじめ、木の上で生活していた類人猿の一部が地上に降りてきました。地面の上で生きていくために、食べ物をたくさん運ぶ必要がありました。その結果、私たちの祖先は立ち上がり、二足歩行を始めたと考えられています。これが約700万年前に登場した「猿人(えんじん)」、つまり最初の人類なのです。
SFの中のもうひとつの星「ミネルヴァ」
小説の中では、かつて火星と木星の間に「ミネルヴァ」という惑星があったことになっています。その星に2500万年前の地球の生き物が運ばれ、そこで進化を続けた人類が、のちに地球に戻ってきた――そんな壮大な物語が展開されるのです。

宇宙ではどんなことが起きていたの?
さて、地球だけでなく、宇宙全体では何が起きていたのでしょう? 私たちの太陽系は、天の川銀河の中を回りながら、「スパイラルアーム(渦巻腕)」と呼ばれる星やガスの帯のような部分を通過します。この帯にはガスがたくさんあり、太陽系がそこを通るとガスが圧縮され、星が生まれやすくなります。
太陽系がこのスパイラルアームを通る周期はおよそ1億年に一度。2500万年前は、ちょうどその通過の時期にあたっていたかもしれません。そのため、星がたくさん生まれる「星形成の活性期」だった可能性があるのです。
星までの距離を教えてくれる「セファイド変光星」
最近の研究では、銀河の中心近くで「セファイド変光星(へんこうせい)」という特別な星が3つ見つかりました。この星たちは明るさが決まったリズムで変わるため、遠くの距離を測る「宇宙のものさし」として使われています。そして、この発見から、2500万年前には銀河の中心近くでも星形成が活発だったことがわかってきました。
おわりに
2500万年前の地球と宇宙には、たくさんの変化と始まりがありました。それがSF小説と結びつくと、もっと面白く、もっとワクワクする物語になります。「過去の地球」と「遠い宇宙」が交差する瞬間を、想像してみてください。それは、私たちの未来につながるヒントになるかもしれません。
関連リンク
・渦巻き腕(リンク)
・最古の霊長類(リンク)
購入リンク
の哺乳類.png)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3a05283e.e3494139.3a05283f.fbb8fbe9/?me_id=1213310&item_id=21000635&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3322%2F9784488663322_1_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

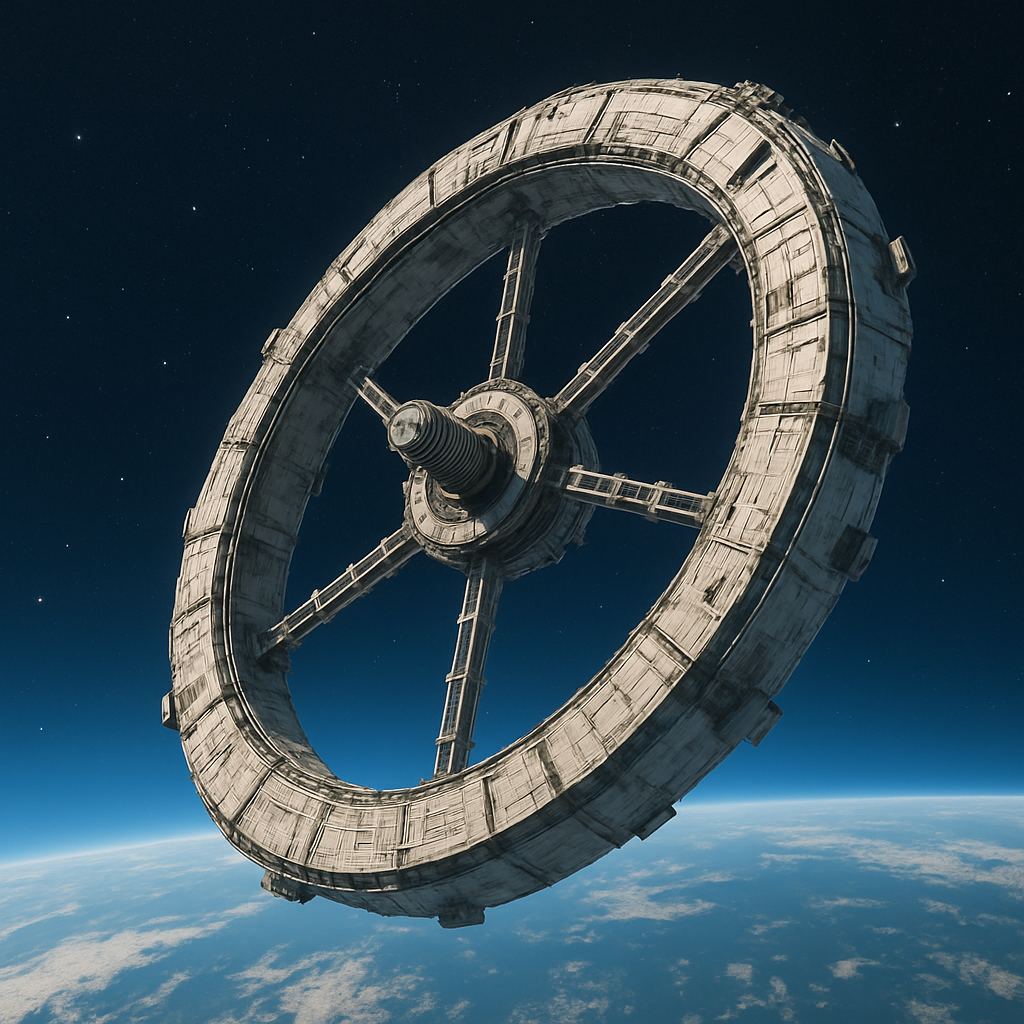

コメント